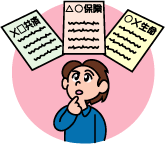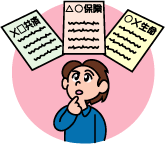[2012-07-26] [2012-07-26]
NKSJ―RM、介護事業者向けRMコンサル提供開始
NKSJグループのリスクコンサルティング会社であるNKSJリスクマネジメント㈱(本社:東京都新宿区、石川秀洋代表取締役社長、以下NKSJ―RM)は、8月1日から「介護事業者向け総合リスクマネジメント支援コンサルティング」の提供を開始する。NKSJ―RMでは、同コンサルティングを通じて、介護施設のリスクマネジメント体制強化を支援し、介護事業者の安全活動に貢献していくとしている。
高齢化社会を背景に、2000年に介護保険制度が発足して十数年が経過したが、その間、施設の利用者やサービス事業者の課題・問題などがクローズアップされている。
特に、介護サービスが従来の措置制度から契約制度に移行したことにより、利用者の権利意識が高まり、介護事故にかかわる苦情・クレームが顕在化してきており、介護事業者への支援ニーズが高まっている。
NKSJ―RMは、損保ジャパンと日本興亜損保を中核会社とするNKSJグループのリスクコンサルティング会社として、いち早く介護事故防止を目的とした、研修を中心とした安全活動支援に取り組んできた。
こうした背景を踏まえ、今回、NKSJ―RMでは、新たに、介護リスクマネジメント担当チームを結成して介護事業者向けリスクマネジメント支援のための要員体制を強化し、介護事業者におけるリスクマネジメントの組織体制構築から運営までを総合的に支援する「総合リスクマネジメント支援コンサルティング」の提供を開始することにしたもの。
同コンサルティングでは、施設におけるリスクマネジメント態勢の現状を分析し、施設の利用者の安心・安全の視点から課題を抽出して、その解決に向けた施設の取り組みを総合的に支援する。
主なコンサルティング・メニューは、①リスクマネジメント態勢の現状分析②リスクマネジメント組織体制の構築支援③リスクマネジメント運用支援(ヒヤリ・ハット分析支援、各種マニュアル作成など)④内部監査導入支援―など。
NKSJ―RMが、医療機関に対する長年にわたる医療リスクマネジメント支援コンサルティングを通して培った経験やノウハウを活用。介護事業者での業務経験のある専門コンサルタントを含めた介護リスクマネジメント担当チームメンバーによる支援を行う。
費用は100万円(税抜)からで、期間は3~6カ月(規模や支援内容により異なる)。年間20件、3000万円の受注を目指す。 |
 [2012-07-25] [2012-07-25]
生保協会、松尾憲治新協会長が会見
生保協会の新会長に就任した松尾憲治氏(明治安田生命社長)は7月20日、生保協会で業界紙向けの記者会見を行い、協会長就任に当たっての所信を表明した。松尾協会長は「少子高齢社会を迎える日本社会に対応して社会保障の整備や財政の健全化が急務となる中、生保業界は公的保障を補完する私的保障の担い手として社会的役割を一層発揮していく必要がある」とし、今後の社会を見据えた取り組みを展開することで安心を届けたいとの考えを強調した。また、昨年3月の東日本大震災での業界の取り組みについて触れ、「震災対応を通じて得た経験を今後の生保事業に生かしていくことが重要だ」と述べた。
松尾協会長は活動の柱として、①生命保険事業への一層の信頼向上と生命保険の普及促進②少子高齢社会に対応した取り組みの検討・推進③国内外の規制などへの適切な対応と事業環境の整備―の3点を挙げた。
生命保険事業の一層の信頼向上と生命保険の普及促進については、東日本大震災への業界一丸となった取り組みを通じて高まった生保事業への信頼をさらに高めるため、業界内での情報共有と社会への情報発信のほか、消費者の意見を各社の経営や教育に反映していくとした。少子高齢社会に対応した取り組みの検討・推進では、消費者の多様なニーズに応えるために金融審議会での意見発信や規制改革要望を続けていくと同時に、高齢層に配慮した手続きやサービスなどの好取組事例を業界内で共有化し、各社の取り組みを後押ししていく姿勢を表明した。国内外の規制などへの適切な対応と事業環境の整備については、国際的な保険監督・規制や国際会計基準、FATCAなどの検討動向をフォローしながら、積極的に議論に参加して働きかけを行っていくとし、具体的には国際会計基準の再公開草案に向けた議論に対する意見発信、死亡保険金の相続税非課税限度額の拡充、今年1月からスタートした新たな生命保険料控除制度の定着化、郵政民営化に関する働き掛けを挙げた。
また、生保協会設立100周年に当たる2008年に会長を務めた前回は、業務改善命令やリーマンショックなどの課題に対応したことを振り返りながら、震災対応が高く評価され、社会が生保の重要性を強く認識している今年また50代目の会長を務めることになったとし、「社会の信頼が増した中で、さらなる信頼の向上に向けた責任を感じる」と述べた。併せて、関連子会社による保育所の運営や現物給付型の商品の開発など、業務範囲の拡大に向けて提言を継続して行っていく方針を示した。 |
 [2012-07-23] [2012-07-23]
住宅瑕疵担保責任保険協会、昨年度保険申込件数約47万件
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人の昨年度の新築の保険契約実績は、保険申込件数が約47万件・保険証券発行件数が約42万件で漸増傾向だったことが住宅瑕疵担保責任保険協会への取材で分かった。リフォーム・既存住宅売買保険の加入実績は合計で、保険申込件数が約7200件、保険証券発行件数が6700件。また、震災関連の取り組みや住宅エコポイントの申請受け付け事業も行った。今後も保険制度の普及に引き続き注力していく方針だ。
住宅瑕疵担保責任保険協会は、保険の適切で安定的な運営を通じて、保険制度と保険法人(現在5社)(注)の信頼性を向上させ、住宅事業者による住宅の瑕疵担保責任の履行の推進と消費者の保護を図るために設立された。
同協会によると、建設事業者が引き渡した新築住宅については、「保険加入」と「保証金の供託」が約半々の傾向が続いている。
同協会では昨年度、東日本大震災の被災地域で三つの取り組みを実施した。
具体的には、「住まいるダイヤルにおける被災地専用フリーダイヤル」「被災地(八戸、仙台、水戸、郡山)での対面相談業務」「相談員が自宅に赴いて行う無料診断・相談業務」で、全相談件数は1万357件に上った。
また、リフォーム瑕疵保険の認知度と利用実績の向上を目的に、リフォーム事業者選択サイト支援事業と連携して、リフォーム事業者検索サイトに登録された事業者の保険料の割引も実施した(昨年7月1日~10月31日)。
さらに、住宅瑕疵保険やリフォーム瑕疵保険などの普及を図るため、各種イベント(第23回住生活月間中央イベント、日経リフォーム博、マンションリフォームセミナー、不動産流通活性化フォーラムなど)に出展し、今春には同協会ホームページ(HP)の全面的なリニューアルも実施。保険法人の保険金支払い事例データを対象とする『住宅の保険事故事例集』(ぎょうせい、2011年3月初版)も発売した。
そのほか、住宅エコポイントの申請受け付け事業については、全国約4000の取次店(今年1月からは約3500)で行い、同協会は郵送による申請受け付けを受け持っている。昨年度の取次実績53万1515件のうち、窓口受け付けは40万5262件、郵送受け付けは12万6253件だった。
今年度は、「前年度から継続している事業を進め、住宅瑕疵担保責任保険制度をさらに普及させるため、中古住宅流通市場やリフォーム市場における同制度の適切・安定的な運用のための事業などに積極的に参加していく」としている。また、国際会議(11月上旬に米国・ニューヨークで開催予定の「国際住宅建設・性能保証連合」の会議)に参加し、各国との情報交換を行う計画。さらに、2017年に日本で開催予定の「第14回国際住宅建設・性能保証会議」の準備に着手する予定で、保険制度の普及に引き続き注力していく方針だ。
【HPリニューアルも実施】
国交省では、中古住宅流通により循環利用されるストック型の住宅市場への転換を図るため「中古住宅・リフォームトータルプラン」をまとめた。
その中で、「中古住宅の流通を促す市場の環境整備」の一つとして売買瑕疵保険の充実・普及促進に取り組んでいる。瑕疵保険・リフォーム保険などに関する情報を提供している住宅瑕疵担保責任保険協会では、普及促進の一環としてこのほどHPの全面改修を実施。リニューアル後のHPでは、瑕疵保険の重要性や同協会の取り組み、提供する保険法人などについて分かりやすく説明している。
(注)保険法人(現在5社)とは、㈱住宅あんしん保証、住宅保証機構㈱、㈱日本住宅保証検査機構、㈱ハウスジーメン、ハウスプラス住宅保証㈱(50音順)。 |
 [2012-07-20] [2012-07-20]
損保協会、コンプライアンスセミナー開く
損保協会はこのほど、損保会館の会議室でコンプライアンスセミナー「保険会社における反社会的勢力への対応」を開催した。日本弁護士連合会・民事介入暴力対策委員会事務局次長の鈴木仁史氏が講師を務め、最近の反社会的勢力対策や暴力団対策法(暴対法)改正の動向について解説した。当日はコンプライアンス委員会委員など約80人が参集した。
現在、各業界では暴排条項が導入され、関係法令の改正や各都道府県の条例が制定されるなど、反社会的勢力対策は大きく進展している。銀行や不動産業界では早くから暴排条項が導入されてきたほか、自動車や宅配業などでも対応が進んでいる。
鈴木氏は「暴対法が制定されて20年が経過し、あからさまに暴力団の威力を示して脅迫する事案は減少したものの、一方で規制を逃れるために暴力団員の数が減少し、準構成員が増加している」と指摘。「反社会的勢力情報の収集のためには警察情報の活用が重要だ」と強調した。
また、暴排条項に基づく契約解除に当たっては、法的リスクやレピュテーショナル・リスクがあることから、条項の説明や周知、情報収集態勢の構築や事実関係の適切な調査などが必要となる。条例上、暴排条項の導入は努力義務だが、「外部委託契約には可能な限り導入することが望ましい」と述べた。
反社会的勢力については、昨年の金融庁の検査事務年度検査方針でも重点的な検証分野とされており、特に未然の取引防止態勢を重点的に検証するよう明記している。鈴木氏は具体的な判例を紹介しながら、昨今の反社会的勢力対策について解説した。 |
 [2012-07-20] [2012-07-20]
富士火災、中小企業向け地震補償拡充
富士火災は7月18日、企業財産包括保険「三冠王Lite」の特約に「地震休業損失等補償特約」などを加えた新商品「三冠王Liteα」を発売した。中小企業向けに地震・噴火による休業リスクをパッケージ商品として提供するのは業界初となる。昨年の東日本大震災を受け、自然災害による事業中断リスクに対するニーズが高いと判断したもので、競争が激しい中小企業マーケットでの取り込みを図る。
新商品は、財産損害をはじめ、利益損失・営業継続費用など幅広い補償を提供する「三冠王Lite」を主契約とし、地震危険による物損害を補償する地震補償特約(地震破裂爆発補償特約と地震水害補償特約)と、新設した「地震休業損失等特約」「噴火補償特約」をセットにして販売する。1981年6月以降に建築された1級・2級構造の建物か、それに収容される什器・備品を保険の対象としており、木造建築物は加入できない。
「地震休業損失等補償特約」は、地震や噴火、また、これらが原因の津波によって保険の対象が被害を受け、営業が休止したり、阻害されたために生じた損失に対して保険金・営業継続費用を支払う。保険金額は1日当たりの粗利益をもとに決め、休業日数を乗じた額を支払う。限度日数に当たる約定復旧期間は通常の「休業損失等特約」と同じ条件になり、支払い限度額(1事故・保険期間共通)を1000万円以上1億円以下の1000万円単位で設定する。免責金額は支払い限度額の2%だが、支払い限度額が5000万円を超える場合は10%を選択できる。
地震リスクに対する保険金の支払い方法は、財産損害・休業損害を合算し、支払い限度額(1000万円以上1億円以下の1000万円単位で設定)を上限として、損害額を実損払いする。
昨今、損保各社では、中小企業向けの火災保険を相次いで投入するなど、競争が激化している。同社では、業界初の補償商品を主力チャネルであるプロ代理店や直販社員を通じてコンサルティング販売する方針で、「BCP対応中小企業向け専用火災保険」として今後の販売拡大に期待を寄せている。
同社企業財物保険部の里見和人部長は「三冠王Liteαの商品優位性を武器に中小企業等開拓の深耕を図りたいと思う」と今後の抱負を語った。
|
 [2012-07-18] [2012-07-18]
AIU、メンタルヘルスと労災でRMセミナー開催
AIU大阪企業保険部は6月13日、リスクマネジメントセミナー「メンタルヘルスの労災認定の実態と企業防衛」を大阪商工会議所(大阪市中央区)で開催した。講師は北浜法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士で大阪市立大学大学院法学研究科特任教授の山本健司氏、同法律事務所外国法共同事業アソシエイト弁護士の村本浩氏の両弁護士が務めた。同一テーマで今年3月にもセミナーを開催しているが、聴講希望者が多数に上ったため、今回の開催となった。当日は人事労務担当の役員や担当責任者ら170人が出席、今回も定員を大幅に上回り、メンタルヘルスに関する関心の高さがうかがえる。
主催者の高橋勝リスクコンサルティング部長は「3月に労災に関するメンタルヘルスセミナーを開催したところ、多数の参加を得た。アンケートでもメンタルヘルスを望む声が圧倒的に強く、今回の開催に至った」とした上で、メンタルヘルスの不調原因について、同氏は管理職者の認識不足、さらに職場のコミュニケーション不足が原因と指摘。その対策として、労務時間の管理、管理職の注意欠如を挙げ、職場でのよい環境づくりに今回のセミナーが役立てば幸いとあいさつした。
セミナーでは、まず、「職場のどこに“うつ病”リスクが潜んでいるのか」をテーマに山本弁護士が講演。現在、自殺者が3万人を超えている中で、自殺の原因や動機の一つに勤務問題が挙げられている。同氏は、これを踏まえ、精神障害などの労災申請が急増している現状を説明し、「職場のメンタルヘルス対策が重要な課題となっている」と職場に潜む“うつ病”のリスクについて言及した。
また、うつ病に至る原因が長時間労働からくるケースと、ハラスメントからくるケースがあるとして事例を挙げた。その中で、会社法に基づく善管注意義務を怠ったとして取締役が損害賠償を請求された大庄事件、長時間労働と会社の責任とした九電工事件を事例に取り上げ、長時間労働と“うつ病”の関係を解説。リスク回避のために何をすべきか、残業事前承認制の導入や残業禁止命令、“うつ病”予備軍のスクリーニングや従業員、特に管理職に対する教育の必要性を強調した。同様に、ハラスメントについての指導とパワハラの違いなどについて述べ、具体的な対応策を示した。最後に、従業員の「うつ」を見つけるための注意点を列挙した。
村本弁護士は「労災をめぐる紛争への対応策」をテーマに、紛争になった場合の企業防衛の事前・事後の観点から講演を行った。
労災事故発生から示談・訴訟までの流れで、①労災申請があった場合の対応②団体交渉の申し入れに対する対応③労働審判申し立てに対する対応―の三つのケースを解説。民事上の請求に先行して、労災の申請を行う場合が多いとして「労災申請があった場合」にどのように対応すればよいのか、業務による心理的負荷に対する考え方、新基準と従来の基準とではどのように違うのか、さらに上積補償やその規定例について述べた。
また、団体交渉申し入れでは、どのような場合に交渉に応ずるのか、交渉におけるポイントと準備について示し、労働審判では、特に手続き申立書が届いたら第1回期日までに準備期間が40日間しかないことに注意し、すぐに弁護士に相談することが重要だと強調した。
|
 [2012-07-18] [2012-07-18]
アメリカンホーム、「心のケア」サポートサービス開始
アメリカンホームは、今年4月に発売した緩和告知型ガン保険「ガンになったことがある方も入りやすい みんなのほすピタる」(引受基準緩和型特約付帯の新・医療総合保険)の契約者を対象とした「心のケア」サポートサービスを6月18日から開始した。これにより同社は、がん経験者の再発による経済的な負担だけでなく、がん再発や悪化などに対する精神的な負担についてもサポートする。
同サービスでは、臨床心理士や精神保健福祉士など心理カウンセラーの電話による無料相談を午前9時から午後8時半まで年中無休で受け付ける。また、面談による相談(完全予約制・1回約50分)にも年3回まで無料で応じる。
「ガンになったことがある方も入りやすい みんなのほすピタる」は、がん経験者でも過去2年以内にがんで入院・手術をしておらず、健康状態に関して一定の条件を満たしていれば申し込むことができる商品。同商品では、今回の新サービスのほか、健康・医療相談から介護・育児に関する相談まで24時間・年中無休で受け付ける「安心ダイヤル24」や、より良い医療の選択のため、日本を代表する各専門分野の名医(総合相談医)に現在の診断に対する見解や今後の治療方針などの意見を聞くことができる「セカンドオピニオンサービス」も無料で利用できる。 |
 [2012-07-11] [2012-07-11]
AIU、役員賠償責任保険を改定
AIUは7月1日、企業の取締役や監査役などの経営陣個人に対する損害賠償請求を主に補償する会社役員賠償責任保険「マネジメントリスクプロテクション」を改定し、補償内容を拡充した。
今回の改定により、従来は補償の対象外としていた会社が主導して役員や元役員を提訴するケースが補償の対象に加わった。
会社役員賠償責任保険(D&O保険)は、会社役員個人が、株主や取引先、従業員から会社法、金融商品取引法、民法に基づく民事責任を追及された際に、刑法違反がないことを前提に、主に損害賠償額を一定金額まで補償する経営保険。しかし、日本企業が一般的に契約しているD&O保険では、契約者である会社自体が被保険者である役員や元役員を提訴するケースについては、補償の対象外となっている。
同社の従来商品でも、株主から提訴要求があった場合に限りオプションで補償対象としていたのを除き、会社による提訴は免責扱いとしてきたが、昨今は企業不祥事の発生時などに、第三者委員会による指摘を受け会社が役員や元役員を提訴するケースが発生するなど経営環境の変化を受けて、会社による提訴も補償の対象とするよう商品内容を改定したもの。
なお、関連した補償として、同社では、2009年の商品改定から、被保険者である役員・元役員が、同じく被保険者であるほかの役員・元役員から善管注意義務や忠実義務を怠ったとして損害賠償請求を受けるケースも補償の対象としている。
また、今回の改定では、保険契約者となる自社やその子会社の役員が、自社の方針を受けて別会社の社外取締役に就任した際に、社外取締役として損害賠償請求を受けるケースも新たに補償対象とした。
同社は、1990年に日本で初めてD&O保険を発売して以降、国内の経営環境に関するリスク要因や法制度の変化に合わせ、補償内容を段階的に拡充してきた。また、同社の親会社であるチャーティスの有する訴訟対策の専門チームと連携することで、契約内容に基づき、米国など海外における日本企業やその経営陣に対する訴訟事案もサポートすることができる。 |
 [2012-07-10] [2012-07-10]
三井住友海上プライマリー生命、「しあわせ未来サービス」開始
三井住友海上プライマリー生命は、7月2日から、無料電話相談「しあわせ未来サービス」を開始した。このサービスは、同社の保険契約者と被保険者を対象として、健康や生活に関するさまざまな相談に応えるもの。各分野の資格者・専門スタッフが、電話で応対する。
「けんこう支援サービス」では、医師・看護師などとの健康相談、医療機関の情報提供、介護、メンタルヘルスに関することなど、幅広く相談できる。また、「せいかつ支援サービス」では、暮らしのトラブルに関する弁護士・社会保険労務士との相談、子育て・妊娠中の悩み、冠婚葬祭、シニアライフ、カルチャー、パソコン・デジタル家電に関する相談まで、幅広いサービスを用意している。
利用時間は、「けんこう支援サービス」が24時間(年中無休)、「せいかつ支援サービス」は月~土曜日の午前10時~午後6時(祝日・年末年始を除く)。 |
 [2012-07-10] [2012-07-10]
損保ジャパン、食品リコール保険に新サービス
損保ジャパンは、グループ会社のNKSJリスクマネジメントと協働で、食品関係の事業者のリコール費用を補償する「フードリコール・プラス」(生産物回収費用保険)の付帯サービスとして「緊急時サポート総合サービス」を開発し、5月から本格的にスタートさせた。食品リコールが発生した場合に必要となる費用を補償するほか、新たにマスコミ対応や商品回収などに関するサービスを提供する。
近年、異物混入による消費者の健康被害などが相次いだことから、食品業界でのリコール件数が急増している。リコールが発生した場合、生産物賠償責任保険(PL保険)に加入していれば、第三者の身体障害と財物損壊に係る法律上の賠償責任を負担することによって被る損害の補償は得られるが、基本補償では、製品の回収費用などは補償されない。損保ジャパンの「フードリコール・プラス」は、通常のPL保険ではカバーされない製品の回収費用や在庫の廃棄費用、社告費用などを補償する。
食品リコールが発生した場合、食品業者は、消費者の安全・安心を守ることを最優先に迅速・的確な組織行動が求められる。しかし、実際に食品フードリコールが発生した場合、「どのように食品リコールを行ってよいのか分からない」「リコール時の対応が心配だ」などの声が寄せられていた。
同社では、食品リコールの際に重要なポイントとなる「スピーディーかつ正確な情報開示」「迅速かつ丁寧な回収措置」「早期かつ適切規模での受け付け態勢」の三つの視点から、食品業者が必要とするサポートを必要なだけ提供することをコンセプトに「緊急時サポート総合サービス」を開発し、2011年10月から提供してきた。提供する主要なサポート機能は①緊急時広報機能支援②物流機能(回収)支援③コールセンター機能支援―の3種類。各機能を連動させる基本パターンによって、円滑なリコールを実現した。リコールが発生し、有責と判断された場合、これらサービスの中からその企業にとって必要なサービスを受けることができる。
また、特長として、それぞれのサポート機能を担当する企業の迅速な対応に加えて、各機能の機動性・実効性を高めるためのコーディネーション機能を付帯していることが挙げられる。これにより、緊急時の広報に関する支援が速やかに行われ、コールセンターの設置・稼働は最速で2営業日、物流(回収)の着手・稼働は最速で3営業日での対応が可能となっている。
同サービスのファイナンス機能については損保ジャパン、コーディネーション機能についてはNKSJリスクマネジメントが担当してきたが、今年5月からは新たに各種サポート機能を担う企業として、㈱ベルシステム(コールセンター機能)、㈱プラップジャパン(緊急時広報機能支援)、ヤマトマルチシステムソリューションズ㈱(物流機能(回収)支援)との提携を正式決定した。NKSJリスクマネジメントの五木田和夫部長は「提携企業はいずれも業界のトップ企業ばかり。安心してサービスを受けていただけるはず」と自信を見せている。
「フードリコール・プラス」では、09年の改定から代理店での取り扱いも開始しており、件数も順調に伸びているという。これまでの販売実績は年間約200件だが、強力な提携をてこに今年度は2倍の400件を目標に販売していきたい考えだ。
損保ジャパン企業商品業務部の新居経治氏は「PL保険に比べて保険料は高めだが、食品リコールの発生頻度は高い。万一、食品リコールが発生すると回収費用は高額となる可能性が高いので、利用価値の高い保険だ」と強調している。
|
 [2012-07-09] [2012-07-09]
アクサ生命、糖尿病支援サービスなど導入
アクサ生命は、7月1日から、新付帯サービス「アクサの糖尿病サポートサービス」と「アクサのメンタルサポートサービス」を導入した。
昨年7月から提供している「アクサのメディカルアシスタンスサービス」は、名医によるセカンドオピニオンや優秀専門医の紹介、24時間電話健康相談サービスなどによる健康と安心のトータルサポートを顧客に届けてきた。
今回、これに加えて2種類の新付帯サービスを導入することにより、顧客に提供できる総合的な医療分野のソリューションを強化する。
「アクサの糖尿病サポートサービス」は、年々増加する糖尿病予備軍に対応し、糖尿病の早期治療・重症化防止をサポートする。
また、「アクサのメンタルサポートサービス」は、企業経営者や従業員のこころの健康をサポートする。これらの新付帯サービスの導入によって、同社の包括的なメディカルアシスタンスサービスが一層強化されることになった。 |
 [2012-07-09] [2012-07-09]
アフラック、「もっとやさしいEVER」発売
アフラックは、7月23日から、引受基準緩和型の医療保険「もっとやさしいEVER」を発売する。
同社は、健康に不安のある顧客でも加入しやすい医療保険として、2007年8月に「やさしいEVER」を発売した後、10年6月には手術保障を拡大し、通院保障も付加できる「新やさしいEVER」を発売した。今回の「もっとやさしいEVER」は、「先進医療特約」や「より求めやすい保険料」「より加入しやすい医療保険」といった、顧客が引受基準緩和型の医療保険に求めるさまざまな要望に応えるため開発したもの。
同商品の主な特徴は、①「先進医療」に対する保障ニーズに応えるため、「やさしい先進医療特約」を新設②1回当たりの支払限度額・通算支払限度額ともに2000万円とした③保険料率の見直しを行い、男女とも全年齢で従来商品より割安な保険料を実現④引受基準を見直し、今まで加入できなかった疾病(うつ病、神経症、慢性肝炎など)を持つ顧客も加入しやすくした⑤告知書の質問項目を再編し、高齢者にも見やすく分かりやすい告知書とした―など。
同社では、今後も顧客の幅広いニーズに応え、顧客の“「生きる」を創る。”をサポートする保険商品の開発に努めていくとしている。
|
 [2012-07-06] [2012-07-06]
金融審、第2回保険商品・サービスの在り方WG開く
金融庁は6月27日、金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ(WG)」(座長=洲崎博史京都大学大学院法学研究科教授)の第2回会合を開き、社会経済の変化に対応する保険商品・サービスや、保険募集の在り方について議論した。保険業界の現状や課題について各委員が意見を述べ、乗り合い代理店の募集行為に対する規制要望や、現物給付型商品への懸念を表明した。
会合ではまず、ボストン・コンサルティング・グループシニアパートナーの加藤広亮委員が国内生保市場の現状を説明。2001年度から11年度までの新契約保険料総額の推移を紹介し、市場規模はほぼ横ばいながら、チャネル構成では銀行窓販や個人向け代理店が成長する一方、生保会社専属の営業社員チャネルが減少傾向にあると指摘した。
また、5年後の新契約保険料は堅調に推移すると予測したものの、生保会社が環境変化に対応し、創意工夫した商品・サービスを提供できるかがポイントになると強調した。
今後、WGで検討を進めていく上で重要なキーワードとして①「家族のための保険」から「自分のための保険」へ②「情報の受け手」から「情報を選択」する消費者へ③「公助」中心から、「私助と公助が共働・連携」する社会へ―の3点を挙げ、今後の規制の在り方について、「限定・制約をベースにした枠組みから、少子高齢化などの状況を踏まえ、国民経済全体に資する“公助・私助の共働・連携”を可能にする官民連携や、各社の創造性・市場開発力を活性化する柔軟なプリンシパル・ベースの規制枠組みへの一層の進化が必要なのではないか」と総括した。
㈱日本格付研究所金融格付部チーフアナリストを務める水口啓子委員は、同WGについての関心事として、①保険業界を取り巻く国内の事業環境の変化②健全性の確保を前提とした保険会社の事業・収益基盤強化に向けたシナリオ③介護関連商品/事業・サービス④新興チャネル⑤さらなる制度整備の検討余地がある分野―の5点を取り上げて意見を述べた。
介護関連商品・サービスについては、公的介護保険の概要や介護サービスの流れを説明してから、留意事項として生保業界で規制緩和を要望している現物給付型保険商品について言及。介護施設への入居権など契約後長期間を経て提供するサービスに対して、インフレーションリスクや、契約者が要介護状態と適合したサービス提供を受けれるかなどの不確実性を指摘した。
また、昨今、消費者ニーズに対応して銀行窓販や来店型代理店(保険ショップ)、ネット比較サイトなど保険募集形態が多様化してきた点を指摘。保険ショップなどの乗り合い代理店については、公平・中立な保険募集を掲げる代理店が存在する一方、代理店ごとに異なる販売方針を持っており、販売手数料などのインセンティブによって消費者の選択がゆがめられる可能性があるとして、今後、新興チャネルでの保険募集にかかる規制の検討を求めた。
全国消費生活相談員協会理事長の丹野美絵子委員は、国民生活センターの統計をもとに、保険関連のトラブル件数が減少していない現状を説明。想定される原因として商品の複雑さ、募集時の説明責任、消費者ニーズとの適合性、支払要件の認知のずれなどを挙げた。
消費者から見た保険の課題としては、「保険商品の簡素化」「募集文書の簡素化」「銀行等金融機関(巨大乗り合い代理店)の販売責任などの明確化」「現物給付型保険への懸念」「消費者教育の必要性」の5点を指摘した。特に銀行窓販チャネルについては、「トラブルが多数出ており、一向に減っていない。消費生活相談の現場からは、保険会社が銀行など金融機関をコントロールできていないと認識している」と強調。募集時のトラブルをなくすために、一定規模以上の乗り合い代理店に対する①商品管理能力、商品の比較選別能力、多種の商品の説明能力などの確保を目的とした制度づくり②金銭的負担など巨大代理店の販売責任の明確化③手数料開示も検討課題に含めた商品選択の公平性の担保―を提案した。
参考人として参加した同志社大学法科大学院の木下孝治教授は、保険商品の販売勧誘にかかる法制を見直す視点として、2009年の保険の基本問題WG「中間論点整理」など、従来の議論の流れを振り返ってから、①販売勧誘の各段階の特質に応じた均整のとれた規制②各種チャネルの行為の特質に応じた均整のとれた規制③商品比較情報の生成・発信コスト低下による規制の隙間を防止④各種チャネルの表示・販売行為に対する保険会社の代位責任の合理化―といった論点を提示。販売主体の規制類型にかかる問題として、乗り合い募集人と保険仲立人の関係を取り上げ、「比較表示・助言を経て募集を行う両者の間に事業モデル上の差異は少ないにもかかわらず、保険仲立人はより多くの規制を受けている。保険仲立人の規制をある程度緩和するべきではないか」と述べた。 |
 [2012-07-05] [2012-07-05]
全労済、住宅損害受付センター新設
全国労働者共済生活協同組合連合会(田原憲次郎理事長、全労済)は、住宅損害受付センターを札幌と福岡の2カ所に設置し、6月1日から24時間365日電話での住宅被災受付を開始した。全労済では、今後も「全労済業務品質基準」に定めた業務の品質向上と効率化を実現し、組合員に最良の業務品質を提供し続け、組合員からの信頼を強固にしていくとしている。 |
 [2012-07-05] [2012-07-05]
生保協会、税制改正で重点要望追加
生保協会は7月3日、平成25年度税制改正に関する要望について、重点要望を追加の上、あらためて取りまとめた。追加した重点要望は次のとおり。
◎遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること。また、税制の抜本的な改革等の中で、相続税制の見直しがなされた場合において、少なくとも現行の非課税措置における対象範囲および水準を維持すること。
(相続税法第12条第1項第5号) |
 [2012-07-03] [2012-07-03]
日本保険学会関西部会、巨大自然災害のリスク管理で報告会開く
日本保険学会関西部会は、6月16日午後1時半から龍谷大学・大阪梅田キャンパスで、2012年度第1回報告会・総会を開催した。巨大自然災害が多発する中、日常生活や産業活動に潜むリスクへの対策を考察するため、報告会では「巨大自然災害のリスク管理:現代社会に潜むリスクを再考する」をテーマに、多方面から4件の報告とそれを基にした質疑応答が行われた。今回の報告会は、従来と異なり幅広い視点からの実施とあって、日本保険学会の江澤雅彦理事長(早稲田大学)のほか役員や会員など37人が参集した。報告会終了後には、総会が開かれた。
報告会では、大阪ガスの藤田祐介氏が「大阪ガスの地震対策」、損保ジャパンの永森満氏が「損害保険会社における巨大自然災害のリスク管理」、三菱重工業の濱崎学氏が「PWR原子力発電プラントの特徴」、筑波大学・滋賀大学の酒井泰弘氏が「想定外を想定する:リスクと不確実性の経済思想」と題して各分野におけるリスクと対策を報告した。
井口富夫部会長は、「昨年の3月11日に起こった地震、津波を念頭に置きながら巨大自然災害の管理を中心に開催し、普段と違った広い角度からリスクを考える」として大阪ガス、損保ジャパン、三菱重工の3社と会員の酒井氏を紹介した。江澤理事長は、「東日本大震災での地震・津波に際してどのような障害が起こったか、リスク対策での知識を共有したい」とあいさつした。
藤田氏は、ガス業界全体の地震防災対策を述べた上で、大阪ガスの防災対策の概要を説明し、トピックスとして災害時の通信施設を紹介した。地震が起こる都度、答申に沿って対応してきた防災対策の策定経緯を、また、阪神・淡路大震災を受けてからの地震防災対策では、予防・緊急・復旧の3段階に分けて示した後、自社の地震防災対策について説明した。特に阪神・淡路大震災を振り返り、供給停止システムの強化実施などを挙げ、予防策としてガス導管の耐震化、さらに緊急対策としての情報収集機能の強化などを説明した。
損保ジャパンの永森氏は、損害保険会社のリスク管理の実施状況や、保険リスクを引き受けるための保険引受リスク量計測手法やVaR(Value at Risk)の定義、リスク量を計算するモンテカルロ・シミュレーションなどを解説した。リスク・コントロールの手法については、再保険、異常危険準備金、キャットスワップ、キャットボンド、再保険プールなどと共に、「保有するリスクの状況を的確に把握し、不測の損失を回避し適切にリスクをコントロールすることで財務の健全性を確保した。リスクと収益を適切に管理し、企業価値の最大化を目的とするERM態勢の構築が損保経営にとって極めて重要だ」とした。
三菱重工業の濱崎氏は、原子力発電(PWR)と火力発電の相違や安全概念について説明し、PWRの安全対策の取り組みを解説した。
「原子力施設の安全確保は“深層防護”(5層の防護)、PWRのSBO(全電源喪失事象)時の炉心冷却は、蒸気発生器への給水と蒸気放出(放射性物質を含まない)で行うことができるのが大きな特長で、さらなる安全対策も実施しており、米国、欧州、ベトナム、ヨルダンなど海外展開を推進している」と述べた。
酒井氏は、関東大震災や阪神・淡路大震災、東日本大震災における著名人の言葉を引用し、「想定外」についての考えを示した。フランク・ナイトの著書「リスクと不確実性および利潤」について説明し、さらに「べき乗則」を解説した。
その中で同氏は、「地震・津波・原発などの巨大災害は、不確実性とどう関係するのか。リスクと不確実性の間には、どのようなつながりがあるのか」について論じ、21世紀に向け「文系リスクと理系リスクとの統合、リスクと不確実性をつなぐ新世紀にふさわしい“新しい総合リスク学”への道が必要」と結論付けた。
報告後、4氏は参加者からの質疑に応じた。会員からは原子力発電に関する質問が集中した。
報告会終了後、今井薫評議員(京都産業大学)が司会を務め、総会を開催した。 |
 [2012-07-02] [2012-07-02]
エルティヴイー、紹介案件向上リバイバルセミナー開く
保険代理店の経営支援事業を展開するエルティヴイーは6月1日、新宿野村ビル(東京都新宿区)で高橋賢二郎氏(ホロスプランニング所属)を招いて紹介案件向上プログラムのリバイバルセミナーを開催した。同セミナーは「続 行列の出来るFP相談所」DVDリリース記念を兼ねて福岡と東京で開かれたもので、7月4日に大阪、18日には札幌での追加開催も決定している。
解説を務めたエルティヴイーの笠原慎也社長は「トップセールスの話を聞いて、分かったつもりになることが多いが、分かることととできることは違う。その差を縮めることがこのセミナーの狙いだ」と説明した。
高橋氏は前職の保険会社コンテストで、顧客契約数全国1位の経験を持ち、自ら営業をしなくても口コミだけで年間150家族が相談に訪れる名物ファイナンシャルプランナー。現在は沖縄県浦添市で一般顧客を対象にFP相談業務を行っている。「訪問しない」「営業しない」「紹介を依頼しない」「保険だけの販売はしない」「夫婦一方だけの相談には乗らない」という厳しい条件を課しているが、毎月15件以上の新規顧客が来訪する。
高橋氏は「保険販売を主軸に置くのではなく、ライフプランニングに重点を置くことで必要な保険が決まってくる」という信条のもとに、ライフプランニンングを行っている。「わたしより業績の優れている人は大勢いるが、わたしよりライフプランニングに熱心に取り組んでいる人はいない」と強調。「ライフプランは夢プラン。夫婦で共通認識を持たなくてはならない。夫婦のやりたいことを聞いていると、だいたい赤字になる。そこで相談者は現実を知って真剣に考え始める。わたしは相談者の最高のライフプラン実現のため、一番大きな夢を叶えるために手伝いたいと考えている。相談していく中で相談者の迷いがなくなれば明確な見直しができる。それがライフプランニングの価値だと考える」とまとめた。
エルティヴイーのHITシリーズでは、DVDの販売とともに講演会を開催しているが、評判は上々だという。笠原社長は「今回のセミナーで、保険が売れる、売れないというのは小さなきっかけだということに気付いたと思う。セミナー参加者の営業の一助となれればと思う」と語った。 |